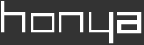ポテトサラダ通信 21
本格ミステリーの貧困?
校條 剛
大学でミステリーの授業を受け持って5年目に入る。最初の二年間は雫井脩介の『クローズド・ノート』の原作と映画をテキストにしていたが、どうやら大学生には内容がウェット過ぎたようで、三年目からテキストを『最後のトリック』(深水黎一郎)に変えた。
大学生は社会人とは違って、実はミステリーをほとんど読んでいない。少なくとも私の教えている大学生は例年そうである。ほとんどの学生が一番馴染んでいるのは、魔法や超能力が使えるファンタジー領域のライトノベル系の小説である。
ミステリーは現実世界を反映したものが多いが、人生経験が少なく、ほぼ学園という狭い社会だけで暮らしてきた学生たちが空想だけで成り立っているファンタジーに馴染むのは理の当然であろう。
リアルな現実感を望まない学生たちに受けるミステリージャンルは、ひと昔前の松本清張が代表する社会派推理小説や現実社会に材をとっている東野圭吾などの作品ではなく、本格とか新本格とか呼ばれる「現実感の薄い、ゲーム的な」ミステリーになる。
『最後のトリック』は、タイトルこそ本格っぽいが実はリアリズムに力点をおいたミステリーだ。<最後の>トリックだけはトリッキーだが、経過部はほとんど「文学」である。
その『最後のトリック』の冒頭にミステリー史の解説がなされている。それを読むと、ミステリーの始まりから爛熟期、そして現在の本格ミステリーの衰退期(?)についての経緯がよく分かる。
大づかみに、本格ミステリー批判部分を紹介しよう――
1 作者だけが答えを知っている殺人事件のトリックだの暗号だのをネタに小説を書くのは卑怯。
2 リアリズムの欠如
どうして犯人は絶海の孤島とか雪で閉ざされた山荘とかで犯行を犯すのか? もしも本当に人を殺して捕まりたくないのならば、暗い夜道で通り魔の犯行にでも見せかければいいのでは? 第一の事件が起こったあとで、警察官や探偵が屋敷のなかをうろうろしているような状況でどうして第二の殺人を犯すのか? また最後の大団円で犯人は状況証拠を指摘されただけで、べらべらと自分の手口をすべて明かしてしまうのか?
3 《意外な犯人のパターン》が出尽くした
犯人=探偵、被害者、死人、動物、事件の記述者、自然現象、こども、その場にいた全員、事件を担当した法医学者など。犯人像は出尽くした感がある。
4 トリックの枯渇
意外な犯人のアイディアがなくなったということは同時に〈初めて試みられたトリック〉がなくなったことを意味する。本格物において、意外な犯人は想像を絶するトリックを創出してきた。だが、斬新なトリックは汲み尽されて、いまや過去のトリックの変形や応用だけが残された可能性ということになってしまったのである。
どうして以上のような状況に陥ってしまったのかというと、本来、本格ミステリーには厳しい掟が課されているからでもある。掟として有名なのは「ヴァン・ダインの二十則」と「ノックスの十戒」がある。
それらの項目をすべて書き連ねることは控えるが、今回、注目しておいてほしい条項だけを記すこととする。
《殺人の方法と、それを探偵する手段は合理的で、しかも科学的であること。空想科学であってはいけない。例えば毒殺の場合なら、未知の毒物を使ってはいけない。》
《自尊心のある作家なら、次のような手法は避けるべきである。これらは既に使い古された陳腐なものである;皮下注射や即死する毒薬の使用》(ヴァン・ダイン)
《未発見の毒薬、難解な科学的説明を要する機会を犯行に用いてはならない。》
(ノックス。ヴァン・ダイン共々ウィキペディアより)
こうした掟を守りながら新鮮なミステリーを思いつくのは確かに難しくなっている。
そこで、今回の本題だ。従来の常識を打破する新しい本格ものが出現という触れ込みで、昨年度話題を集めた新作ミステリーが登場した。
昨年(2017年)「鮎川哲也賞」を受賞し(つまり新人)、年末恒例の〈このミステリーがすごい!〉〈週刊文春ミステリーベスト10〉〈本格ミステリ・ベスト10〉という三つのランキングのNo.1に選ばれた『屍人荘の殺人』である。
私がこの作品を知ったのは新聞の記事を読んでからであり、昨年末のこうした動きは感知しなかった。大学という世間から少し奥まった聖域で暮らしていたせいだろうか。
それはともかく、ほかの読むべき本を押しのけて、そのミステリーを読んでみたのである。
唖然! だった。唖然のほかに言葉を知らない。いや、呆れたという言い方もあるか。それほどにもヒドイと私には思える小説がミステリー界で大歓迎されていることに対して疑問符しか付かなかったのである。
誰か同好の士がいるはずだと、フェイスブックで『酷い小説を読んだ』と発言したところ、「友達」になっているあるミステリー評論家から「傑作ですぜ」という反応があった。もう一人親しい評論家は「炎上しますよ」と忠告してくれた。しかし、フェイスブックの友達の輪を出来るだけ狭くしている私ごときの発言では簡単に炎上はしないようだ。やはりホリエモンくらいの大物が言わなくちゃいけない。
まあ、ここでストーリーやトリックや一番問題な「クローズド・サークル」の説明なんぞはしないほうが紳士的というものだろう。この本はかなり売れているようで、親しい編集者もいる東京創元社が儲かってくれるのはありがたいということもある。私が願うのは、ともかく本を買って、読んでほしいということだ。そして、一緒に憤慨してほしいというわけ。